セメント資料館
Cement Archives
セメント・コンクリート用語辞典
Glossary
あ
| アーウィン (-) |
水硬性物質。化学組成は、3CaO・3Al2O3・CaSO4(C4A3S)で表され、自然界にも産出する鉱物。1200℃の低温で生成するが、1350℃以上では分解する。 |
|---|---|
| 圧縮強度 (あっしゅくきょうど) |
単純圧縮応力状態の下でのコンクリート破壊強度のこと。通常は、一軸圧縮載荷時の最大耐力を、加力軸に直交する供試体断面積で割った値(N/mm2単位)で表す。単にコンクリートの強度といえば圧縮強度をさし、しばしばコンクリートの品質一般の指標としても用いられる。
→強度* |
| アルカリ骨材反応 (-こつざいはんのう) |
セメント中のアルカリ(Na、K)が、コンクリートを内部から崩壊させる現象。セメントに含まれる空隙水*中のアルカリ度が上がることで、骨材中のSiO2質が溶けはじめ、毛細管空隙*水中のCa2+やNa2+、K2+とSiO2により、寒天のようなゲル状物質を生成させる。それが吸水、膨潤して、その膨張圧により、コンクリートを内部から崩壊させてしまう。 |
| アルミネート相 (-そう) |
セメント原料*を焼成して得られるクリンカー鉱物の一つ。アルミン酸三石灰(3CaO・Al2O3)に近い化学組成をもつ。水との反応が急激で、瞬時に多量の熱を放出し瞬結してしまうため、ポルトランドセメントには凝結調節剤として石膏*が加えられている。アルミネート相は、1日の強度の発現に作用する。ダムなどのマスコンクリート*には水和熱を抑制するために、アルミネート相の少ない中庸熱ポルトランドセメント *などが使われている。 →間隙質 |
| アルミン酸カルシウム (-さん-) |
酸化アルミニウム(Al2O3)と酸化カルシウム(CaO)の化合物の総称。セメントクリンカー中ではアルミネート相*などを指す。 |
| 亜瀝青炭 (あれきせいたん) |
瀝青炭*より石炭化度が低く、褐炭*との中間的な品質の低い石炭。 →褐炭* |
| アンハイドライト (-) |
無水石膏*の英語表現 |
い
| イオン電荷 (-でんか) |
イオンのもつ電荷*は、電気素量(電子の電荷)の整数倍であるが、その数と符号をいう。元素のつくるイオンでは、イオン電荷に周期的性質がある。たとえば、アルカリ金属やアルカリ土類金属がハロゲンとつくるイオン性化合物では、同族元素のイオン電荷はすべて等しい。イオン電荷の大きさが2以上のイオンを多価イオンともいい、構成元素の酸化数と密接な関連がある。 |
|---|
う
| 打ち込み (うちこみ) |
練り混ぜ、運搬されたコンクリートやモルタルを、型枠内の所定の位置にいきわたらせる作業のこと。広義には締め固めを含む場合もある。 |
|---|
え
| 液相 (えきそう) |
→相* |
|---|---|
| エトリンガイト (-) |
セメント水和物の一つ。化学式3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2Oで表される化合物の鉱物名。AFt*と表記されることもある。 セメントが水和する時、セメント中のアルミネート相*と石膏*との反応で水和初期に針状結晶として析出する。エトリンガイトはそれ自体で強度を発現し、高硫酸塩スラグセメントや超速硬セメントでは、初期強度の発現をエトリンガイトに依存している。また、エトリンガイトは析出により、セメント硬化体を膨張させる性質がある。この性質が、アルミネート相の多いセメントの硫酸塩により崩壊する原因になっている。 水和してエトリンガイトを生成する化合物をセメントに添加して、膨張セメントとすることもできる。 →AFt* |
| エフロレッセンス (-) |
結露や雨水に溶解したセメントペースト中のNa、Kイオンが、水滴の乾燥した後に、Na2CO3、K2CO3やCaCO3などの炭酸塩がコンクリート表面に白いシミとなって残る現象。エフロレッセンスは、溶液が蒸発した後に残る滓の意味で、白華*とも呼ばれる。 |
| エーライト (-) |
セメントクリンカーの主要鉱物。セメント原料*を1260〜1450℃の高温で焼成した際に生成する。珪酸三石灰(3CaO・SiO2)に近い組成をもち、微量成分*としてマグネシウム、ナトリウム、カリウム、鉄などが固溶している。普通ポルトランドセメント*中には約50%のエーライトが含まれており、1〜28日の強度発現に関係する。アリットともいう。 |
| エントラップドエア (-) |
AE剤*などを用いない場合でもコンクリートの練り混ぜ時に混入する気泡*。通常のコンクリートには、1mm以上の大径のものが0.5〜3%程度存在する。 |
| エントレインドエア (-) |
AE剤*やAE減水剤*などの使用による表面張力*の低下で、コンクリート中に持ち込まれ安定する30μm〜1mm程度の気泡*。これらの混和剤*を計画的に使用し、耐凍結融解性を向上させたものがAEコンクリートである。 |
お
| オージェ電子分光法 (-でんしぶんこうほう) |
表面分析に用いる電子分光法*の一種。AES(Auger Electron Spectroscopy)ととも呼ばれる。通常2keV程度の電子線を固体表面に入射させて、散乱電子のエネルギー分析をし、オージェ効果による放出電子を検出する。固体のごく表面に存在する不純物元素の同定や、吸着種の分析に利用される。 |
|---|---|
| 落口 (おちぐち) |
セメント焼成キルンの最終部分、クーラ入り口。 →ロータリーキルン* |
| 小野メソッド (おの-) |
クリンカーの焼成度の品質評価を顕微鏡観察により行う方法。 |
| オパール (-) |
蛋白石ともいう。理想化学組成はSiO2・nH2Oで、粒径150〜300nmのシリカコロイド球が最密充填した塊状鉱物。H2O量は2〜13%(通常3〜9%)の範囲で変化する。 |
か
| 界面活性剤 (かいめんかっせいざい) |
液体と液体、液体と固体など、二つの相間の表面に吸着して、湿潤、浸透、洗浄、起泡、乳化など、表面の性質を著しく変える性能を持った物質のこと。表面活性剤ともいう。一般のコンクリートに用いられている界面活性剤には、AE剤*、減水剤*、高性能減水剤*などがある。 |
|---|---|
| 嵩比重 (かさひじゅう) |
物質の質量を、その物質粒の空隙を含むかさ容積で割って求めた比重*。 |
| 価数 (かすう) |
→原子価* |
| 褐色クリンカー (かっしょく-) |
クリンカー内部の色調が黄褐色を帯びたもの。セメントクリンカーの色調は通常灰黒色であるが、このようなクリンカーが生成する事がある。還元焼成雰囲気に起因して生じる事が多い。品質上の問題はない。 |
| 褐炭 (かったん) |
腐植炭の一種で、石炭化度の最も低い石炭。一般には黒褐色ないし帯褐黒色だが、暗炭が多く、不粘結。瀝青炭*と比較して水分・腐植酸・酸素が多く、炭素が少ない。一般用炭として使用される。最も品位の低い石炭。→表−1参照 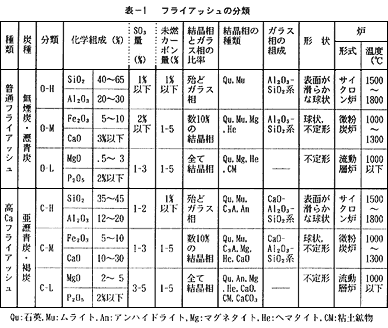
|
| 窯 (かま) |
=セメント焼成キルンのこと。 →ロータリーキルン* |
| 窯尻 (かまじり) |
セメント焼成キルンの導入部分。 →ロータリーキルン* |
| ガラス (--) |
液相*を結晶化させることなく冷却して、その粘度が固体と同じ程度の大きさに達した非晶質*(無定形)物質。 |
| 間隙質 (かんげきしつ) |
セメントクリンカー鉱物。セメントクリンカーを偏光顕微鏡*で観察すると、エーライト*やビーライト*の間をうめる物質が見られるが、これを間隙質という。アルミネート相*およびフェライト相*を主体とした物質である。 |
| 還元 (かんげん) |
一般に酸化*の反対の過程。本来は酸化された物質を元に戻すことをいう。広くある物質が電子を得る過程で、還元されることに対応する。 |
| 乾燥収縮 (かんそうしゅうしゅく) |
コンクリートやモルタルが、硬化過程や硬化後に乾燥にともなう水分の逸散によって縮む現象。主にセメントペースト中の空隙水*が蒸発することによって生じる。 |
き
| 偽凝結 (ぎぎょうけつ) |
セメントは注水後、5〜10分で軽いこわばりを生じ、再び軟化するが、この後に見られる正常な凝結*現象をいう。原因は二水石膏*の生成、間隙質*の急激な水和によるものとされている。 |
|---|---|
| 生石灰 (きせっかい) |
酸化カルシウム(CaO)のこと。 →水酸化カルシウム* |
| 気泡 (きほう) |
エンラップドエア*やエントレインドエア*など、30μm程度以上の気体でうめられた空隙*のこと。 |
| 凝結 (ぎょうけつ) |
モルタル、コンクリートなどが流動体から固体に変化すること。自形を保つが強度を発現しない状態をいう。 |
| 供試体 (きょうしたい) |
材料や構造体の性質を調べるための試料(片)のこと。コンクリートを構造物に打ち込む前に同じコンクリートでつくったり、構造物から抜き取るなどして試験をする。「テストピース」ともいう。 |
| 凝集エネルギー (ぎょうしゅう--) |
分子やイオン、原子などが集合した状態(液体または固体)にある物質の原子を、無限遠までひき離すのに必要なエネルギーのこと。 |
| 強度 (きょうど) |
コンクリートなどの材料や、鉄筋コンクリートなどの構造物や構造部材が、外力の作用によって降伏したり破壊される時に示す最大の耐力のこと。材料の強度は、単位面積当たりの荷重を示す応力の単位で表される。強度は、力学的性質の中で最も重要なものの一つである。荷重の種類に応じて圧縮強度*、引張強度、曲げ強度*、せん断強度などに区分される。なお、単にコンクリートの強度といえば圧縮強度を指す。 |
| キルン (--) |
セメント原料*を焼成*してクリンカーを製造する窯のこと。 →ロータリーキルン* |
く
| 空隙 (くうげき) |
セメント硬化体中の気泡*のこと。気泡は、気体で満たされた隙であり、練り混ぜの際に取り込まれるエントラップドエア*およびAE剤*などを使用した場合に連行導入されるエントレインドエア*である。また、これとは別に、水で満たされた水隙がある。水隙は、硬化セメントペースト中で水和生成物によって満たされない毛細管空隙*およびC-S-H*水和物の層間に相当するゲル空隙*である。 |
|---|---|
| 空隙水 (くうげきすい) |
セメント水和物と結合せずに、セメントペースト中の空隙に存在する自由水*のこと。 |
| クリストバライト (--) |
シリカ鉱物に属する同質多形の一種。α-クリストバライト(低温型)と、β-クリストバライト(高温型)がある。α-クリストバライトを常圧下で加熱すると、198〜240℃でβ-クリストバライトにかわる。 |
| クリンカー (--) |
セメント原料*を窯(キルン*)で高温焼成して得られる焼結物塊のこと。セメント原料を加熱していくと1,000℃以下で粘土鉱物*の脱水と熱分解、石灰石*粉末の脱炭酸が起こる。950〜1200℃でビーライト*の一部、1200〜1300℃でアルミネート相*およびフェライト相*、1260〜1450℃の高温でエーライト*が生成する。これらの水硬性化合物がクリンカー中に含まれており、セメントの強度を発現することになる。クリンカーに石膏*を3〜5%加え粉砕することによりセメントが製造される。 |
| クリンカーアッシュ (--) |
石炭ボイラーなどで、石炭の灰が溶融してガラス*状またはスラグ*状になったもの。 |
| 群晶 (ぐんしょう) |
同じ種類の鉱物粒子が多数集まって生成している状態。 |
け
| 珪酸カルシウム (けいさん--) |
酸化カルシウム(CaO)と二酸化珪素*(SiO2)の化合物の総称。セメントクリンカー中ではエーライト*、ビーライト*などがある。 |
|---|---|
| 珪酸率 (けいさんりつ) |
「Al2O3+Fe2O3」に含まれる「SiO2」の割合のこと。珪酸率が大きくなると、出来上がったクリンカーは間隙質*よりビーライト*を多く含むようになるため、強度発現のおそい長期強度型のセメントとなる。SM(SilicaModulus)ともいう。 |
| 珪石 (けいせき) |
珪酸(SiO2)分を供給する原料として用いられる工業上の鉱物および岩石の総称。 |
| 結合材料 (けつごうざいりょう) |
骨材*など、非接着性の粒子間に介在して接着性を発現し、一体化するための材料。 |
| 結合水 (けつごうすい) |
結晶水や水和水など、いろいろな結合状態にある水のこと。液体の水(自由水*)に対する語。 |
| 結晶 (けっしょう) |
原子や分子などの三次元的な周期的配列により構成されている固体物質のこと。結晶格子*構造をとる。 →ガラス* |
| 結晶格子 (けっしょうこうし) |
結晶*の並進要素の同価点を結んでできる三次元的格子のこと。 |
| ゲル (--) |
ゾル*(コロイド溶液)がジェリー状に固化したものをいう。多量の水などの液体成分あるいは空隙を含むことが多いが、系全体にわたる支持構造をもち、その形状を保つ。 |
| ゲル空隙 (--くうげき) |
硬化セメントペーストにおいてC-S-H*の層間に相当する直径3nm以下の空隙*のこと。 |
| 原子価 (げんしか) |
ある元素の原子が、他の原子と単結合をいくつ作れるかを表した数。これらを、それぞれの原子または元素の原子価という。 |
| 減水剤 (げんすいざい) |
表面活性剤の一種。所定のコンシステンシー*を有するコンクリートを得るため、必要な単位水量の減少を目的とする混和剤*のこと。セメント粒子の凝集を解き、それを分散させたり、湿潤させることによって減水効果が得られる。したがって、所要のスランプ*を得るのに必要な単位水量*を減ずることができる。この結果として、強度*、耐久性*、水密性が増大する。また、材料分離やブリージング*が減少するなどの性能を付与することもできる。 |
| 懸濁液 (けんだくえき) |
液体中にコロイド粒子、または顕微鏡で見える程度の固体粒子が分散したもの。とくにコロイド粒子分散系は、ゾル*と呼ばれる。 |
| 原単位 (げんたんい) |
単位量(一般に質量)の製品を生産するために必要な原料や電力エネルギーの量。 |
こ
| 高温高圧養生 (こうおんこうあつようじょう) |
高温高圧窯(オートクレーブ)を用いた促進養生方法。高圧蒸気養生などともいう。通常、温度180℃前後、蒸気圧は10atm程度の条件で処理する。 |
|---|---|
| 硬化 (こうか) |
モルタル、コンクリートが凝結後、時日の経過に伴って硬度と強度を増すこと。 |
| 光学的性質 (こうがくてきせいしつ) |
物質の光に対する性質のこと。光線透過率、屈折率、蛍光、光学活性などがある。 |
| 剛性 (ごうせい) |
変形に対する抵抗性のこと。応力とひずみ、作用力と変形との関係をいう。 |
| 高性能減水剤 (こうせいのうげんすいざい) |
コンクリートの流動性*を著しく高める混和剤*のこと。高流動化剤とも呼ばれる。この性質を利用して、通常のコンクリートと同等のワーカビリティー*を保ったまま単位水量*を減少することができるため、高強度のコンクリートが得られる。 |
| 降伏値 (こうふくち) |
ビンガム流体で、流動をまさに開始する時の応力値を表すレオロジー*定数。軟練りコンクリートのスランプ*を支配しているといわれている。 |
| 高炉スラグ (こうろ--) |
製鉄所の溶鉱炉(高炉)で鉄を精錬する際、同時に生成する鉄以外の不純物が集まった非金属質鉱物。人工骨材、高炉セメント*原料などとして利用する。 |
| 高炉セメント (こうろ--) |
高炉スラグ*とポルトランドセメントクリンカーに、少量の石膏*を加え粉砕したセメントのこと。JISでは、高炉スラグ*の分量により、A種(5〜30%)、B種(30〜60%)、C種(60%〜)に分類される。3〜7日の初期強度は低いが、長期強度*は普通ポルトランドセメント*を上回る場合もある。 |
| 固相 (こそう) |
→相* |
| 骨材 (こつざい) |
モルタル、コンクリートを造るため、セメントおよび水と練り混ぜる材料のこと。砂、砕砂、砂利、砕石、その他これに類似するものをいう。 |
| 固溶体 (こようたい) |
異なる物質が均一に溶け合った固相*をいう。全組成にわたって固溶体をつくる場合と、限られた組成範囲だけで固溶体をつくる場合がある。 |
| コロイド (--) |
物質が、普通の光学顕微鏡では認められないが、原子あるいは低分子より大きい粒子として分散した状態のこと。 |
| コンクリート (--) |
セメント、細骨材*、粗骨材*、水を練り混ぜて造られたもの。混和剤*、混合材*を加えたものもコンクリートという。 |
| 混合材 (こんごうざい) |
セメント、水、骨材以外の材料で、多くは無機質粉末である。練り混ぜの際に必要に応じてコンクリートやモルタルなどに加えられる材料のうち、使用量が比較的多く、その容積をコンクリートの配合計算で考慮する必要のあるものをいう。一般に知られているものとしては、フライアッシュ*、スラグ*、シリカ*微粉末などがある。 |
| 混合セメント (こんごう--) |
ポルトランドセメントに、各種混合材*を配合し、耐蝕性、乾燥収縮*、耐久性*などを改善したセメントの総称。高炉セメント*、シリカセメント、フライアッシュセメント*などがある。混合剤には、石灰石*粉、ドロマイト、消石灰*、高炉スラグ*、フライアッシュ*、珪酸白土などが使われる。ポルトランドセメントに比べ、作業性、水密性が良く、初期の強度は低いが長期的には優れた強度を示す。化学抵抗性、耐熱性にも優れた特性を持つものが多い。 |
| コンシステンシー (--) |
固まる前のコンクリートが持つ性質の一つ。主に水量の多少によるセメントペースト、モルタル、コンクリートの軟らかさの程度を表す用語。 |
| 混練水 (こんれんすい) |
コンクリート練り混ぜに際し、ミキサ内に投入する水のこと。 |
| 混和剤 (こんわざい) |
セメント、水、骨材以外の材料で、練り混ぜの際に必要に応じてコンクリートやモルタルなどに加えられる材料のうち、使用量が比較的少なく、それ自体の容積がコンクリートの配合計算において無視されえるものをいう。一般に知られているものとしては、AE剤*、減水剤*、AE減水剤*、高性能減水剤*、凝結調整剤、防錆剤などがある。 |
さ
| 細骨材 (さいこつざい) |
骨材の粒径が5mm以下のもの。示方配合においては、細骨材は5mmふるいを全部通るものをいう。 |
|---|---|
| 最密構造 (さいみつこうぞう) |
同じ大きさの球を最も密に積み重ねた構造、およびその球の中心を格子点とする結晶構造のこと。充填構造ともいわれる。 |
| 材齢 (ざいれい) |
コンクリートなどを打ち込んでから、ある時期までの経過時間をいう。「材令7日」とは、打ち込んでから満7日を経たことを意味する。 |
| 酸化 (さんか) |
一般に、広く電子を奪われる変化またはそれに伴う化学反応をいう。本来は、ある純物質が酸素と化合すること。また、ある純物質が水素を失った場合も酸化といわれる。 →還元* |
| 三成分系混合セメント (さんせいぶんけいこんごう--) |
ポルトランドセメントに高炉スラグ*微粉末、フライアッシュ*など、2種の混合材を用いて混合したセメントのこと。コンクリート構造物の耐久性*向上や、マスコンクリート*の低発熱化が図れる。 |
し
| ジェットセメント (--) |
添加剤により、凝結時間を任意に設定できるセメントのこと。普通、ポルトランドセメント*の材令3日に相当する強度を数時間で発現することができる。従来のポルトランドセメントのクリンカーに含まれるエーライト*、ビーライト*、フェライト相*のほかに、アルミネート相*に代わるクリンカー鉱物としてカルシウム・フルオロアルミネート(C11A7・CaF2*)を含むクリンカーと無水石膏*および微量の添加剤からなる。当社の商標。 |
|---|---|
| しきい値 (--ち) |
反応その他の現象を起こさせるため、系に加えなければならない物理量の最小値のこと。 |
| 実積率 (じっせきりつ) |
容器に満たした骨材の絶対容積と、その容器の容積との比の百分率。 |
| 重金属 (じゅうきんぞく) |
密度*が比較的大きい金属。4.0g/cm3以上のものを指すことが多い。また、長周期型周期表の1B〜5Bの金属元素を指すこともある。 |
| 収縮応力 (しゅうしゅくおうりょく) |
収縮に起因する応力のこと。コンクリートの乾燥収縮ひび割れなどに関連する。 |
| 自由水 (じゆうすい) |
結合水*や水和水のように何らかの束縛を受けている水に対する語。 |
| 蒸気養生 (じょうきようじょう) |
一般には、コンクリートの硬化促進の目的で行う常圧蒸気養生のことをいう。通常の製品工場で広く用いられている。 |
| 焼成 (しょうせい) |
原料を窯(キルン*)などに入れて高い温度で焼き、化学反応を促してクリンカー*をつくること。 |
| 焼成雰囲気 (しょうせいふんいき) |
→ロータリーキルン* |
| 消石灰 (しょうせっかい) |
=水酸化カルシウムの別名。 |
| 焼点 (しょうてん) |
→セメント焼成キルンの最終部分付近で、燃料を燃やしている部分のこと。 →ロータリーキルン* |
| シリカ (--) |
=二酸化珪素 |
| シリカフューム (--) |
SiO2を主成分とした粒径0.1μm程度の球形をした超微粒子の産業副産物。フェロシリコンや金属シリコンの製造時に発生する廃ガスを集じんすることにより得られる。 |
| 親水基 (しんすいき) |
水に対して親和性を示す原子団をいう。静電気的相互作用や水素結合などによって水分子と弱い結合をつくる。水酸基(OH)、カルボキシル基(COOH)、アミノ基(NH2)、カルボニル基(CO)、スルホ基(SO3H)などの極性基や解離基を含む原子団がその性質を示す。 →疎水基* |
す
| 水銀圧入ポロシメーター (すいぎんあつにゅう--) |
水銀細孔計ともいう。多孔質固体の細孔容積Vpとその径の分布をもとめる装置。細孔径をdpとしたとき、水銀圧入時の圧力p=-4σcosθ/dp(r:σ:表面張力、θ:接触角)より求める。 |
|---|---|
| 水硬性 (すいこうせい) |
加えた水と反応し、大気中や水中で固まる性質のこと。 |
| 水硬率 (すいこうりつ) |
(SiO2+Al2O3+Fe2O3)に対するCaO、または(SiO2+Al2O3+Fe2O3)に対する (CaO-0.7SO3)の割合。水硬率が大きいクリンカーほどCaO含有量が大きく、エーライト*が多く生成するので、短期強度*が高く水和熱の大きなセメントができる。HM(Hydraulic Modulus)ともいう。 |
| 水酸化カルシウム (すいさんか--) |
化学式Ca(OH)2で表される化合物で、消石灰とも呼ばれる。石灰石*を焼いて得られる生石灰*(CaO)が水と反応して生成される。水酸化カルシウムは、ポルトランドセメント中のカルシウムシリケートの水和の際にも生成し、ポルトランドセメントが完全に水和するとセメントの重量の20〜30%が水酸化カルシウムとなる。 |
| 水中養生 (すいちゅうようじょう) |
供試体を恒湿の水槽中に完全に浸せきする養生のこと。 |
| 水和 (すいわ) |
セメントと水が反応して不溶性の水和物を作り、凝結硬化する現象。 |
| 水和熱 (すいわねつ) |
セメントと水との反応は発熱反応であり、この反応熱を水和熱という。ダムや部材厚が大きいコンクリートでは、水和熱により温度が上昇し、温度応力によりひび割れが生じることがある。 |
| スラグ (--) |
=高炉スラグ |
| スランプ (--) |
コンクリートのスランプ試験において、スランプコーンを引上げた後のコンクリート頂部の下り。固まる前のコンクリートのコンシステンシー*の指標として、最も広く用いられている。スランプはコンクリートが自重によって変形を起こそうとする力と、これに抵抗する力が釣り合ったときに定まるもので、降伏値*と密接な関係がある。 |
| スランプロス (--) |
コンクリートのコンシステンシー*が練り混ぜ後、時間とともに低下していくこと。スランプ*の経時的な減少をいう。 |
せ
| 石英 (せきえい) |
理論化学組成はSiO2。シリカ鉱物の代表。 |
|---|---|
| 石灰石 (せっかいせき) |
広大な層をなして産する方解石の集合物。古代の生物の遺骸や貝殻などが堆積してできた堆積岩であり、炭酸カルシウム(CaCO3)を主成分とする。石灰石は焼成されると、約900℃で二酸化炭素(CO2)と酸化カルシウム(CaO)に分解される。 |
| 石灰飽和比 (せっかいほうわひ) |
ある温度と圧力における石灰の溶解度の積と、飽和溶解度の積との比のこと。 |
| 石膏 (せっこう) |
一般には、二水石膏のこと。結晶水の相違により無水石膏(CaSO4)、焼石膏(半水石膏 CaSO4・1/2H2O)、二水石膏(CaSO4・2H2O)に分類され、それらには各種の変態がある。その種類には、天然石膏、化学工業の副産石膏、排煙脱硫装置から発生する石膏があるが、我が国は天然石膏が乏しいため、ほとんど化学石膏か排煙脱硫石膏*が使用されている。用途は、建築材料から医薬品まで広範囲だが、セメントの原料としては、二水石膏が凝結調整剤として使用される。 |
| セメント (--) |
一般には、土木、建築工事用に用いるポルトランドセメント、混合セメント*、アルミナセメントなどの 水硬性*セメントを指す。また、広義にはアスファルト、膠(にかわ)、樹脂、石膏*、石灰、ポルトランドセメントなど有機質、無機質、金属質またはこれらを組み合わせた接着剤の総称。 |
| セメント原料 (--げんりょう) |
石灰石*、粘土*、珪石*、鉄原料、石膏*のこと。石灰石は酸化カルシウム(CaO)、粘土は二酸化珪素(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)および酸化第二鉄(Fe2O3)を供給し、珪石は不足した二酸化珪素、鉄原料は不足した酸化第二鉄をそれぞれ補充している。 |
| セメントペースト (--) |
セメントと水とを練り混ぜてできたものをいう。単にセメントと水のみでなく、各種の混和剤を含んだものもセメントペーストと呼ぶ。 |
| 遷移帯 (せんいたい) |
骨材とセメントペースト界面となる骨材周辺部分に観察される不連続な領域のこと。Caに富んだ水和物からなる空隙量の大きな部分である。 |
そ
| 相 (そう) |
明確な物理的境界により、他と区別される物質系の均一な部分。この部分が気体であれば気相、液体なら液相、固体では固相と呼ばれる。 |
|---|---|
| 早強ポルトランドセメント (そうきょう--) |
普通ポルトランドセメント*に比べて早期に高い強度を発現し、長期にわたっても強度が増進する特性を持つもの。緊急工事や高強度を要求される場合に用いられる。短期強度*(1〜3日)の発現を高めるために化学組成としてエーライト*の含有量を60%以上に保つよう原料を配合(調合)し、焼成などに十分配慮される。 |
| 走査電子顕微鏡 (そうさでんしけんびきょう) |
略称SEM(Scanning Electron Microscope)。収束電子線を試料表面上に走査して、各走査点から放出される電子を検出器に受け増幅し、走査と同期させてブラウン管上に像として写し出す装置である。像の焦点深度が大きいため表面の地形的観察に多く用いるほか、各走査点から放出されるオージェ電子や特性X線をとらえて微小領域の元素分析装置としても用いられている。 |
| 相対湿度 (そうたいしつど) |
大気中に存在する水蒸気と、その状態の大気が含みうる最大限度の水蒸気の量との割合。単に湿度ということもある。 |
| 増量材 (ぞうりょうざい) |
コンクリートの性能をあまり損なわずに多量に使用できる混合材*のこと。 |
| 粗骨材 (そこつざい) |
5mmふるいに重量で85%以上とどまる骨材のこと。砂利、砕石、高炉スラグ*砕石、人工軽量骨材などがこれに含まれる。 →細骨材* |
| 疎水基 (そすいき) |
水分子を排除して、水となじみにくい原子団のこと。アルキル基(CnH2n+1)、フェニル基(C6H5) などがその例である。 →親水基* |
| 塑性粘度 (そせいねんど) |
ビンガム流体で、流動を開始した後の粘度を表すレオロジー*定数のこと。数値が大きいほど流動抵抗が大きく、ニュートン流体の粘性係数に対応する。コンクリートでは、単位セメント量*が多く、水セメント比*が小さいほど塑性粘度が大きいといわれている。 |
| ゾル (--) |
液体を分散媒とし固体を分散粒子とするコロイド*。コロイド溶液といわれることもある。 |
た
| 耐久性 (たいきゅうせい) |
コンクリートが使用に耐えられる年月によって定められるコンクリートの性質。コンクリートが種々の物理的および化学的作用によって、腐食または破壊される程度で定まる。 |
|---|---|
| 打設 (だせつ) |
打ち込み*と同義語。RC示方書では「打ち込み」を用いている。 |
| 単位水量 (たんいすいりょう) |
表乾状態にある骨材を用いて、コンクリート1mをつくるときに使用する水の重量。 |
| 単位セメント量 (たんい--りょう) |
コンクリート1m3をつくるときに必要なセメントの重量。 |
| 短期強度 (たんききょうど) |
とくに材令初期の硬化の過程にあるコンクリート強度のこと。初期強度、早期強度ともいう。コンクリート強度は材令の経過に従って増大する。 →長期強度* |
| 炭酸塩 (たんさんえん) |
炭酸(H2CO3)の塩で、炭酸イオン(CO32-)をふくむイオン結晶物質。正塩(MI2CO3)、水素塩(MIHCO3)と水酸化物塩(MI2CO3・nMIOH)とがある。 |
| 断熱温度上昇 (だんねつおんどじょうしょう) |
マスコンクリート*と同様な状態で養生*するため、コンクリートがもっている熱量を極力外へ放熱しないように供試体*を断熱的に包んだ場合の温度上昇。単位セメント量*が220kgのコンクリートでは、普通ポルトランドセメント*で33〜42℃、低発熱セメント*ので25〜30℃程度の断熱温度上昇がある。 |
ち
| 中庸熱ポルトランドセメント (ちゅうようねつ--) |
水和熱の低いポルトランドセメント。ダム、橋梁、巨大構造物などに用いるマスコンクリート*では、水和熱による内部温度の上昇が温度応力によるひび割れ発生の原因となるので中庸熱ポルトランドセメントが使用される。セメントが水和する際に発生する水和熱を小さくするため、発熱量が多いエーライト*とアルミネート相*を極力減らし、長期強度*の発現をつかさどるビーライト*を増やしたもので、含有量はビーライトが35〜42%、エーライトが36〜40%、アルミネート相が4〜7%程度である。普通ポルトランドセメント*に比べて短期強度*は低いが、長期強度は同程度で乾燥収縮*が小さく、耐硫酸性や化学抵抗性が大きいなどの優れた特性をもっている。また、普通ポルトランドセメントに比べて、混和剤の吸着量が少ないため、流動性が向上する。 |
|---|---|
| 長期強度 (ちょうききょうど) |
コンクリート強度は一般に材令28日のものが基準とされるが、長期強度は材令のうち、3ヵ月、6ヵ月、1年あるいはそれ以上のコンクリート強度をいう。短期強度*の対比語。 |
つ
て
| 低発熱セメント (ていはつねつ --) |
水和硬化の際に、発熱量が小さいポルトランドセメントのこと。エーライト*を少なくし、ビーライト*を多くしたものである。混合セメント*として発熱量を小さくしたものもある。ダム工事のような大量施工では発熱量が大きいと温度上昇が激しいので、低発熱セメントが使用される。 |
|---|---|
| 鉄率 (てつりつ) |
Fe2O3に対するAl2O3の割合。鉄率が大きいとAl2O3分が多くなるので、クリンカー中のアルミネート相*の生成量が多くなり、短期強度*が高く水和熱の大きな化学抵抗性の小さいセメントができる。逆に、鉄率が小さいとFe2O3分が多くなるので、アルミネート相が少なく、フェライト相*が多くなり、短期強度は低く水和熱の小さな化学抵抗性の大きいセメントが得られる。IM(Iron Modulus)ともいう。 |
| 電荷 (でんか) |
すべての電気現象の根元となる実体。その性質は、電気量によって規定される。電荷という言葉を電気量の意味に用いることもある。電気ともいい、閉じた系の電気量の代数和は不変である(電荷保存則)。 →イオン電荷* |
| 電子顕微鏡 (でんしけんびきょう) |
電子線を用いて試料の拡大像を得る装置。この中には試料を透過した電子を、電子レンズを用いて結像する透過型、試料表面で反射した電子を結像する反射型、集束電子線を試料表面上に走査して各走査点からの2次電子を用いて像を作る走査電子顕微鏡*、加熱あるいはイオン照射によって試料から放出される電子を結像する表面放出型(電界イオン顕微鏡)などがある。 |
| 電子分光法 (でんしぶんこうほう) |
物質に光やX線のような電磁波、電子やイオンのような荷電子粒子や励起電子をあて、発生する電子の運動量分布、運動量分布、運動エネルギー分布、その角度分布などを測定して物質の物理状態を調べる方法の総称。励起光照射源により異なった情報が得られるので、入射線の種類に応じた名称でよぶことが多い。原子や分子の電子状態や振動状態、とくに内殻電子のエネルギー状態や電荷分布、固体内電子のふるまい、固体表面や吸着分子の状態について多様な知識が得られる。また、電子検出感度を高めることにより、微量試料の検出も可能なため、分析分野をはじめ、有機化学、生化学などの微量試料を扱う分野での検出、同定、構造解析などにも応用される。1960年代当初、これらの化学的研究に、X線を照射源としたX線光電子分光法が用いられ、とくにESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)と呼ばれた。現在でもこの名を使うことがある。 |
と
| トバモライト (--) |
スコットランドのトバモリーで発見された天然鉱物。組成は5CaO・6SiO2・5H2Oで示される珪酸カルシウム水和物の一種。トバモライトは組成がC-S-H*に類似しており研究の参考にされている。 |
|---|---|
| トランジション・ゾーン (--) |
=遷移帯*の英語表記 |
| トリディマイト (--) |
珪酸鉱物の一種。鱗珪石ともいう。化学組成は「SiO2」。高温型、中間型、低温型の3種が知られており、それぞれの間の転移温度(常圧)は163℃と117℃である。 |
な
に
| 二酸化珪素 (にさんかけいそ) |
化学組成は「SiO2」。温度、圧力によって多くの類形が存在する。シリカというのは俗称である。 |
|---|---|
| 二水石膏 (にすいせっこう) |
石膏*の一種。化学組成は「CaSO4・2H2O」。 |
ぬ
ね
| 粘土 (ねんど) |
岩石や鉱物のうち、砂より細かいものの総称。土壌構成粒子の機械的分析では、普通直径0.01mm以下のものを粘土分と呼ぶ。主成分は二酸化珪素*(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)、酸化第二鉄(Fe2O3)で、セメントの原料としても用いられる。 |
|---|---|
| 粘土鉱物 (ねんどこうぶつ) |
粘土*を構成する主成分鉱物。結晶質と非晶質*(アロフェンなど)に分類されるが、大部分は2μm以下の微細な層状珪酸塩である。 |
の
は
| 排煙脱硫石膏 (はいえんだつりゅうせっこう) |
硫黄酸化物(SOx*)による公害を防止するため、発電所や工場などに設けられた排脱装置から副生する石膏*。排脱石膏、脱硫石膏ともいう。 |
|---|---|
| ハイパフォーマンス・コンクリート (--) |
信頼性の高い構造物の構築を目的に開発されたコンクリートのこと。ひび割れなどの初期欠陥を生じるおそれが小さく、長期にわたり優れた耐久性*が得られる。日本では特に、東大の岡村甫教授らのグループが開発したコンクリート技術として知られる。高粉体量、高性能AE減水剤*の使用などにより、施工過程における人的要因による悪影響を受けないため、打設時における締固め作業を行わずに型枠の隅々にまで充填でき、均質なコンクリートが造れる。 |
| パイプクーリング (--) |
コンクリートに埋め込んだパイプに冷たい水を通し、コンクリートを冷やすこと。 |
| 白色セメント (はくしょく-) |
セメントの製造過程で、成分中に含まれる鉄分を少なくした白色のポルトランドセメント。物性的には普通ポルトランドセメント*とほぼ同じであるうえ、白色であるため、化粧モルタル、タイルの目地詰めなどに用いられる。当社の商標。 |
| 白華 (はっか) |
→エフロレッセンス* |
| 反射電子像 (はんしゃでんしぞう) |
試料に照射した電子線を、半導体検出器に受け増幅して得た画像のこと。試料に照射した電子線の一部は、反射電子または後方散乱電子となり、高いエネルギーを保持したまま再び試料外へ散乱されて出てくる。その強度は試料を構成する元素の原子番号に依存するため、原子番号が大きい部分ほど反射強度は強く、反射電子像では明るく表示される。組成像ともいう。 |
| 半水石膏 (はんすいせっこう) |
石膏*の一種、CaSO4・0.5H2O |
ひ
| 比重 (ひじゅう) |
ある温度で、ある体積を占める物質の質量と、それと同体積の標準物質の質量との割合をいう。液体、固体に対しては標準物質として、普通4℃における水を採用する。 →密度* |
|---|---|
| 非晶質 (ひしょうしつ) |
物質内部の原子配列に、周期性が存在しない物質のこと。 →ガラス*、結晶* |
| 比熱 (ひねつ) |
単位質量の物質の温度を単位温度だけ上昇させるのに要する熱量。普通は、1g(または1mol)、1K(℃)に対する値を用いる。単位は、J/K・gまたはJ/K・mol。 |
| 比表面積 (ひひょうめんせき) |
粉末の単位体積、重量当たりの表面積のこと。 |
| 表面エネルギー (ひょうめん --) |
液体、固体の表面は半面を異種の物質で囲まれているので、内側とくらべて高いエネルギー状態にある。表面が持つこの過剰エネルギーを表面エネルギーという。 |
| 表面張力 (ひょうめんちょうりょく) |
液体はその表面をできるだけ小さくしようとする傾向をもち、外力の作用が無視できるときは球形をとる。これは液体の分子間にはたらく引力にもとづいて、液体表面に沿い一種の張力がはたらくためである。これを表面張力といい、液体の表面に平行に、液面上の単位長さの線に直角にはたらく応力として表される。 |
| ビーライト (--) |
セメントクリンカー鉱物。セメント原料を焼成して得られる。珪酸二石灰(2CaO・SiO2)に近い組成をもち、微量成分*としてマグネシウム、ナトリウム、カリウム、鉄などが固溶している。普通ポルトランドセメント*中には約30%のビーライトが含まれている。ベリットともいう。 |
| ビーライトセメント (--) |
一般には、ビーライト*含有量が50%以上のポルトランドセメントを指す。超低発熱型セメントの必要性や混和剤*とセメントの相互作用の研究から、ビーライトを多くしたセメントの優れた物性が認知され、特に高流動コンクリート分野で注目され始めた。当社により、我が国では最初に実製造、事業化されている。 |
| 微量成分 (びりょうせいぶん) |
量が変化しても、鉱物組み合わせに影響をあたえないほど少量の成分。 |
ふ
| 風化 (ふうか) |
セメント粒子が空気中の湿気と反応して、軽度の水和作用を受けること。風化が進むと、生成した水酸化カルシウム*が空気中の炭酸ガスと化合して炭酸カルシウムとなる。一般にセメントが風化すると比重*が小さくなって強熱減量が増し、凝結*に異常をもたらすほか、強度が低下する。 |
|---|---|
| フェライト相 (--そう) |
セメント原料*を焼成して得られる鉱物。鉄アルミン酸四石灰(4CaO・Al2O3・Fe2O3)に近い組成をもち、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなどが固溶している。普通ポルトランドセメント*中には約10%のフェライト相が含まれている。間隙質*の1相。 |
| 複屈折 (ふくくっせつ) |
一般に、光学的異方性を持つ媒質に光が入射するとき、2つの屈折光が現れる現象をいう。 |
| 複合材料 (ふくごうざいりょう) |
いくつかの素材を組み合わせて作った材料。素材の組み合わせ(複合)により、単一の材料より優れた特性を持つものをつくり出すことができる。 |
| 普通ポルトランドセメント (ふつう--) |
土木、建築工事、各種コンクリート製品の製造などに最も多く使用されているセメント。セメント全生産量のほとんどを占め、単にセメントといえば、この普通ポルトランドセメントを指す。主要成分は、1日〜28日の強度に関係するエーライト*が約50%、28日以降の長期強度*に寄与するビーライト*が25%を占め、長短期においてバランスのとれた強度を発現する。 |
| フライアッシュ (--) |
ポゾラン*の一種で、火力発電所の微粉炭燃焼で産する副産物。それ自体に水硬性*はないが、セメントに混入使用すると、フライアッシュ中のシリカ*質が、セメントの水和反応によって生成される水酸化カルシウム*と徐々に反応し、不溶性の安定な珪酸カルシウム*などの化合物を作る性質(ポゾラン反応)がある。そのため、長期にわたって強度が増進し、水密性や耐久性*が向上する。また、フライアッシュの粒は、ほぼ球形をしているとともに表面が滑らかなため、コンクリートのワーカビリティー*を改善する効果も大きい。 |
| フライアッシュセメント (--) |
フライアッシュをポルトランドセメントクリンカーおよび少量の石膏*と混合粉砕、またはセメントと均一に混合したもの。JISでは、フライアッシュの分量によりA種(5〜10%)、B種(10〜20%)、C種(20〜30%)に分類されている。フライアッシュは約20〜30μmの球状粒子で、モルタル、コンクリート中では、ボールベアリングの作用をして流動性*を向上させる。 |
| フラー・トンプソン曲線 (--きょくせん) |
粒子を最密充填にするための粒度分布曲線。フラー(W.B.Fuller)とトンプソン(S.E.Thompson)によって確立された。 |
| ブリージング (--) |
練り混ぜ水の一部が骨材、セメント粒子の沈降に伴って上面に集まってくる現象。比重差に起因する材料分離の一種。 |
| フリーライム (--) |
セメント原料*を焼成した時に、二酸化珪素*や酸化アルミニウムと反応せずに残った遊離酸化カルシウム(CaO)のこと。f.CaOと略す。未反応石灰、遊離石灰ともいう。 |
| プレクーリング (--) |
コンクリートの練り上がり温度を低くするため、コンクリートの材料をあらかじめ冷やすこと。 →パイプクーリング* |
| ブレーン比表面積 (--ひひょうめんせき) |
セメントの粉末度*を表す値。通常、セメント1g当たりの表面積で示す。求め方はJIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定するブレーン空気透過装置を用い、セメントを詰めたセルの中を通過する空気の速さを溶液ヘッドの変化時間で求め、標準試料との比較計算で算出する。普通ポルトランドセメント*で3100〜3400cm2/g程度を示し、早強性セメントは、これより高い値を示す。 |
| フロー (--) |
モルタル、コンクリートの軟度、流動性*を示すもの。JIS R 5201 (セメントの物理試験方法)では、フローテーブルを用いるフロー試験によって測定することとされる。 |
| 分光光度計 (ぶんこうこうどけい) |
分光器で得られるスペクトルの強度分布を光電管、光センサーなどを用いて電気的に測定する装置。波長領域により赤外、可視紫外、遠紫外などに分類される。吸収、発光、反射、蛍光など、多種類の測定に用いられる装置が製造市販されている。 |
| 粉末度 (ふんまつど) |
粒子の細かさの程度を示す値。 →ブレーン比表面積* |
へ
| ヘスの法則 (--のほうそく) |
一連の化学反応における反応熱(符号を含めて)の総和は、その反応の始めの状態と終わりの状態だけで定まり、その途中の経路によらないという法則。総熱量不変の法則ともよばれる。ヘス(G.H.Hess)が提案した(1840年)。この法則は、エネルギー保存則(熱力学第1法則)から当然の結果として導かれるものであるが、歴史的にはそれに先んじて発表された。直接に測定することの困難な反応熱の決定に利用される。 |
|---|---|
| ヘマタイト (--) |
赤鉄鉱のこと。化学組成は「Fe2O3」。比重*は5.26と大きい。自然界に産出し、最も重要な鉄鉱石鉱物である。フライアッシュ*中にも認められる。 |
| 偏光顕微鏡 (へんこうけんびきょう) |
偏光を使う光学顕微鏡の一種。岩石片や鉱物片の観察をはじめ、広く結晶の光学的性質*を調べるために用いられる。 |
| 変態 (へんたい) |
同一の化学組成でありながら、温度や圧力の相違、生成条件が異なるために物理的性質や原子配列を異にする物質の各状態をいう。 |
ほ
| 膨張材 (ぼうちょうざい) |
水和反応によって、エトリンガイト*や水酸化カルシウム*を生成し、これが主な膨張源となって、モルタルやコンクリートを膨張させる作用のある混合材*をいう。その種類は、カルシウム・サルフォアルミネート系、石灰系、石膏・石灰系などに大別される。 |
|---|---|
| 補色 (ほしょく) |
2つの光を適当な割合で加法混色したもの。色刺激が白色の色刺激と等しくなる時に、はじめの2つの光の色は互いに補色であるという。 |
| ポゾラン (--) |
フライアッシュ*、けい酸白土、けい藻土、火山灰などのシリカ*質微粉末で、それ自体に水硬性*はないが、セメントに混合した場合、セメントの水和反応によって生じる水酸化カルシウム*と反応して不溶性の化合物を生成するポゾラン反応を起こす物質の総称。ポゾランを用いれば、セメントの水和反応によって生じる発熱を緩和できるため、一般にマスコンクリート*に用いられることが多い。この場合、若材令の強度はポゾランを混合しないコンクリートに比べ小さいが、長期強度*はポゾラン反応の進行にともない順次増加していく。 |
| ポルトランドセメント (--) |
エーライト*、ビーライト*、アルミネート相*、フェライト相*を主成分とする水硬性セメントのこと。石灰石*、粘土*を主原料に、珪石*、酸化鉄原料を加えて1400〜1500℃で焼成したクリンカーを急冷した後、緩結剤として3〜5%の石膏*を加えて微粉砕して作られる。1824年、英国のアスプジン(J.Aspdin)により発明、特許出願された。我が国で製造されているポルトランドセメントには、普通*、早強*、超早強、中庸熱*、耐硫酸塩ポルトランドセメントがあり、品質はJIS R 5210(ポルトランドセメント)に規定されている。 |
| ポンパビリティー (--) |
固まる前のコンクリートをコンクリートポンプを使用してパイプ輸送する場合の圧送の難易度のこと。 |
ま
| 前養生期間 (まえようじょうきかん) |
工場で型枠にコンクリートを成形後、蒸気を送るか加熱を開始するまでの期間。送蒸待時間、放置期間などともいわれる。配合(調合)、形状、寸法、外気温などにもよるが、一般に2〜4時間程度を指す。前養生をとらないで急激な加熱を行うと、ひび割れを生じ強度不足を招くことがある。前養生が短いほど、ゆるやかな加熱が必要になる。乾燥収縮*や中性化などの試験に供するまでの養生期間も前養生期間という。 |
|---|---|
| マグネタイト (--) |
磁鉄鉱のこと。化学組成は「Fe3O4」。比重*は5.2と大きい。ヘマタイト*と並んで重要な鉄鉱石鉱物である。フライアッシュ*中にも認められる。 |
| 曲げ強度 (まげきょうど) |
はり供試体の曲げ試験によって得られる破壊時の最大曲げモーメントを、断面係数で割って求めた引張縁の応力の最大値。曲げ強度試験は、間接引張強度試験の一種であり、曲げ強度は、はり供試体を細長い弾性体と仮定して求めた引張強度である。 →強度* |
| マスコンクリート (--) |
ダムや橋梁などで大塊状に施工されるコンクリートのこと。JASS5では部材断面の最小寸法が80cm以上で、かつ水和熱によるコンクリートの内部最高温度と外気温との差が25℃以上になることが予想されるコンクリートをいう。 |
| マトリックス (--) |
異成分からなる複合体の中で、独立した大結晶粒子や骨材のまわりにあり、それらを結合している地の部分。コンクリートでは、セメントペーストやモルタルの部分をいう。 |
み
| 水セメント比 (みず--ひ) |
セメントペースト、モルタル、コンクリートにおける水とセメントとの重量比。セメント重量に対する有効水量の百分率。W/Cと表すこともある。 |
|---|---|
| 密度 (みつど) |
一つの“量”が空間、面または線の上に分布しているとき、微小部分に含まれる“量”の体積、面積、長さに対する割合をいう。それぞれ、体積密度、面密度または線密度とよんで区別する。一般には体積密度をさす。単に密度というときは、質量についての密度をさす。 →比重* |
| 未反応石灰 (みはんのうせっかい) |
=フリーライム*ともいう。 |
| ミル (--) |
原料、メントクリンカーを粉状に粉砕する機械。用途別に原料工程では「原料ミル」、セメント粉砕工程では「仕上げミル」という。また、形式別に、予備粉砕用のローラーミルやローラープレス、たて型で粉砕効率の高いたて型ミルがある。現在では乾燥も行えるたて型が主流となっている。 |
む
| 無煙炭 (むえんたん) |
最も石炭化がすすんだ石炭。揮発分が少ないため、煤煙を出さず短炎または無炎で燃焼する。非粘結。 →褐炭* |
|---|---|
| 無水石膏 (むすいせっこう) |
石膏*の一種。化学組成は「CaSO4」。 |
| ムライト (--) |
化学組成は「2Al2O3・SiO2」。「Al2O3」と「SiO2」の割合は、3:2ないし2:1である。Al2O3とSiO2の化合物は高温でのみ安定である。自然界ではまれだが、磁器などにはごく普通に見られる。 |
め
| メリライト (--) |
ゲーレナイト(Ca2Al2SiO7)とオケルマナイト(Ca2MgSi2O7)の連続固溶体*のこと。自然界ではカルシウムが豊富な溶岩中などに産出するが、カルシウムの多いスラグ*中にも多量に存在する。 |
|---|---|
| 面間隔 (めんかんかく) |
結晶格子*において、平行な一組の格子面群の相隣る平面間の距離。 |
も
| 毛細管空隙 (もうさいかんくうげき) |
硬化セメントペースト中で、水和生成物によって満たされない隙に相当する直径3nm〜30μm程度の空隙*。 |
|---|---|
| もどり粉 (--こ) |
セメントクリンカーの閉回路粉砕において、分級分離されたクリンカーの粗粒物(50〜80μm)のこと。 |
| モノサルフェート水和物 (--すいわぶつ) |
化学組成は、「3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O」。水和初期においてアルミネート相*と石膏*が反応して生成されるエトリンガイト*は、石膏がすべて消費されるとアルミネート相と反応して次第にモノサルフェート水和物に変化する。AFm*と表記されることもある。 |
| モルタル (--) |
セメントと細骨材*(砂)とを水で練り混ぜたもの。左官仕上げに用いられることが多い。 |
や
ゆ
| 誘導期 (ゆうどうき) |
エーライト*の水和過程における二つの発熱段階のうち、水と接触してから数分以内の急速な水和反応に続いて起きるゆるやかな水和反応の間の数時間をいう。 |
|---|
よ
| 溶解度積 (ようかいどせき) |
水に溶けてイオンに分かれる電解質MV1XV2は飽和溶液中では次のように解離している。MV1XV2⇔v1Mz1+v2Xz2-このとき、溶液中のイオンの濃度[Mz1+]v1と[Xz2-]v2の積KSPを溶解度積という。ここでz1、z2はイオンM、Xの価数であり、v1z1=v2z2の関係がある。溶解度積は温度、圧力だけによる定数であって、難溶性塩の溶解度積は化学分析とくに沈殿滴定において重要な値である。 |
|---|---|
| 溶解熱 (ようかいねつ) |
定温定圧で溶質が溶媒に溶けるときに発生または吸収する熱量のこと。混合熱の一種である。 |
| 養生 (ようじょう) |
コンクリートの硬化作用を十分に発揮させるため、適当な温度と湿度を確保し、外力が加わらないように保護しておくこと。コンクリートの圧縮強度*は養生温度によって変化する。 |
ら
り
| 律速段階 (りっそくだんかい) |
化学反応などの動的過程がいくつかの段階によって構成されているとき、そのうちの一つが他の段階に比べて緩慢に進行することで、全過程の進行が実際上支配されてしまうような段階をいう。 |
|---|---|
| 流動性 (りゅうどうせい) |
固まる前のコンクリートの流れやすさを示す性質。コンシステンシー*とは不可分の関係にある。コンシステンシーが主として水量の多少による流れやすさ、軟らかさを評価するのに対し、流動性という場合には水量の影響のほか、セメントや骨材粒子間の摩擦、かみ合いなどの影響が考慮される。 |
| 粒度調整セメント (りゅうどちょうせい) |
多量の混合材*(有機混和剤)を用いて、低水セメント比で流動性*に優れた高強度のコンクリートを得ようとするセメントのこと。セメントの粒度分布をブロードにし、1μm程度の微粒をシリカフューム*、石灰石*粉、分級フライアッシュ*で、また、50μm以上の粗粒をミルもどり粉*、その他の粉末で置き換え、セメントを最密充填が可能な連続粒度分布に調節することで造られる。 |
る
れ
| レオロジー (--) |
物質の変形と流動に関する科学と定義される。1922年アメリカの化学者ビンガム(G.Bingham)が提案した名称で、ギリシャ語のreo(流れるの意)に由来する。流動学と訳されることもある。レオロジーで扱われる対象は、化学的に複雑な組成または構造を持ち、力学的にも固体と液体との中間的性質を示すようなものが多い。これらの物質や、その物質を含む溶液について観測される現象としては、異常粘性、塑性、チキソトロピー、粘弾性などがある。 |
|---|---|
| 瀝青炭 (れきせいたん) |
光沢ある黒色を呈し、黄色の長炎をあげてもえる最も代表的な石炭のこと。石炭化度は褐炭*と無煙炭*の中間。 →褐炭* |
| 連行空気 (れんこうくうき) |
→エントラップドエア* |
ろ
| ロジン・ラムラー式 (--しき) |
ロジン(Rosin)とラムラー(Rammler)が、1933年に石炭粉砕物の粒度分布をあらわす関数として見いだした計算式。粒度の通過分積算重量割合をyとするとy=1-exp{-(x/x')n}となる。ここでnは粒度分布関数、x'は粒度特性値(代表粒径)であり、この2定数で粒度分布が定まる。x軸とy軸にlog
Dとlog{log(100/R)}の目盛りをつけたロジン・ラムラー線図にプロットすると直線となり、勾配nは粒度の均一性をあらわすことになる。 →n値* |
|---|---|
| ロータリーキルン (--) |
セメント原料*を焼成*する窯。耐熱レンガを内張りした鋼鉄製の円筒管 (径3〜6m、長さ60〜200m、傾斜2.5〜5%)をしている。原料は上端より供給され、下端で燃料を燃やして加熱する。原料は窯の回転に伴って徐々に下方へ移動し、高温焼成される。 →図参照 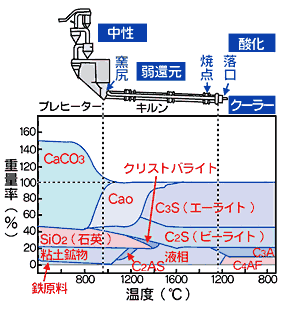 クリンカー鉱物生成工程 |
わ
| ワーカビリティー (--) |
主に、固まる前のモルタルやコンクリートの作業性の程度のこと。「ワーカブルなコンクリート」とは、作業性のためにほどよい軟らかさを持ち、しかも材料分離しにくいコンクリートのことをいう。 |
|---|
A
| AE剤 (えーいーざい) |
界面活性剤*の一種。界面活性作用のうち起泡性の優れたものをいい、モルタルやコンクリートに微細な気泡*を連行し、ワーカビリティー*や耐久性*向上のために用いられる混和剤*である。コンクリート中に、球状に近いためボールベアリング的作用とクッション的役割を果たす1〜100μm程度の微細な独立気泡を連行する。適量の気泡を連行したコンクリートでは、ワーカビリティーが良くなり、所要のコンシステンシー*を得るための水量が減少する。また、材料分離やブリージング*が減少し、凍結融解に対する抵抗性が増大するなどの優れた性能を発揮する。 |
|---|---|
| AE減水剤 (えーいーげんすいざい) |
AE剤*と減水剤*の性能を兼ね備えた混和剤*のこと。連行空気*によるAE効果と分散作用による減水効果が重なり合い、AE剤単体よりも更に大きな減水効果が得られる。そのためコンクリートのワーカビリティー*の改善、耐久性*向上の効果がAE剤および減水剤を単体で用いた場合よりも大きくなる。 |
| AES | Auger Electron Spectroscopyの略称。=オージェ電子分光法 |
| AFm | カルシウム・アルミノフェライト・モノサルフェート水和物型化合物の総称。カルシウムイオン、アルミニウムイオン、特に硫酸根は種々のイオンと置換することができ、多種の同型化合物がある。 →モノサルフェート水和物* |
| AFt | カルシウム・アルミノフェライト・トリサルフェート水和物型化合物の総称。カルシウムイオン、アルミニウムイオン、特に硫酸根は種々のイオンと置換することができ、数多くの同型の化合物がある。 →エトリンガイト* |
B
C
| C11A7・CaF2 | 化学組成は、「11CaO・7Al2O3・CaF2」。 |
|---|---|
| C2S | 化学組成は、「2CaO・SiO2」。 →ビーライト* |
| C3A | 化学組成は、「3CaO・Al2O3」。 →アルミネート相* |
| C3S | 化学組成は、「3CaO・SiO2」。 →エーライト* |
| C4AF | 化学組成は、「4CaO・Al2O3・Fe2O3」。 →フェライト相* |
| Ca(OH)2 | =水酸化カルシウムのこと。 |
| C-S-H | CaO-SiO2-H2O(珪酸カルシウム水和物)の略称。セメント水和物の大半は「Si」に対する「Ca」の割合が1.0〜2.0程度のC-S-Hである。 |
D
| D-乾燥 (でぃー・かんそう) |
水蒸気圧5×10-4mmHg下(-80℃の飽和水蒸気圧)で乾燥すること。主にコンクリート中の自由水*が除去される。 |
|---|
E
| EPMA | Electron Probe Micro Analyserの略称。 →X線マイクロアナライザー* |
|---|---|
| ESCA | Electron Spectroscopy for Chemical Analysisの略称。 →電子分光法* |
F
| f.CaO | =フリーライム* |
|---|
G
H
| HM | Hydraulic Modulusの略称。 =水硬率* |
|---|---|
| HVFC | High Volume Fly Ash Concreteの略称。 |
I
| IM | Iron Modulusの略称。 =鉄率* |
|---|
J
K
L
M
| μm | 長さの単位。10-6(百万分の一)メートル(1mmの千分の一)のこと。μ(マイクロ)は10-6を表す接頭語。「ミクロン」は「マイクロメートル」の慣用名。 |
|---|
N
| n値 (えぬち |
粉体の粒度分布をロジン・ラムラー線図にプロットした時の直線の勾配を表す値。値が大きいほど粒度が均一であることを示す。 →ロジン・ラムラー式* |
|---|---|
| New RCプロジェクト (にゅー・あーるしー --) |
建設省総合技術開発プロジェクト「鉄筋コンクリート造建築物の超軽量・超高層化技術の開発」の略称。昭和63年から平成4年度までの5か年間にかけて行われた。 |
| nm | 長さの単位。10-9(十億分の一)メートルのこと。n(ナノ)は10-9を表す接頭語。 |
| NMR | Nuclear Magnetic Resonance(核磁気共鳴)の略称。原子核のスピンによる磁気共鳴のこと。核スピン共鳴ともよばれる。化学シフトやスピン-スピン結合の観測から、物質中の原子配置、電子構造、分子の微細構造などに関する情報が得られる。 |
| NOx | 一般に、一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)の総称。工場、火力発電所などの固定発生源、自動車エンジンなどの移動発生源から燃焼反応にともなって生じ、大気汚染や酸性雨の原因となる物質のこと。 |
O
P
| pH | 水素イオン指数を意味する記号。セーレンセン(S.P.Sorensen)は、水溶液中の低濃度の水素イオン濃度を表すために、pH=-log10[H+]を定義し、水素イオン指数とよんだ(1909年)。[H+]は水素イオンのモル濃度(mol/dm3) を表す。25℃、中性では[H+]=[OH-]=10-7mol/dm3なので、pH=7となる。酸性はpH<7、アルカリ性はpH>7となる。 |
|---|
Q
R
S
| SEM | Scanning Electron Microscope(走査電子顕微鏡*)の略称。 |
|---|---|
| SM | Silica Modulusの略称。 =珪酸率* |
| SOx | 一般に、二酸化硫黄(SO2)や無水硫酸(SO3)など、硫黄の酸化物の総称。石油や石炭の燃焼などにより発生し、大気汚染や酸性雨の原因になる物質のこと。 |
T
| TMS | Tetramethylsilane(テトラメチルシラン)の略称。化学組成は、「 (CH3)4Si」。四塩化珪素と過剰量のメチルグリニャール試薬の反応で作られる。融点-102℃、沸点27℃。核磁気共鳴(NMR*)スペクトルの化学シフトの標準物質として用いられる。 |
|---|
U
V
W
| W/C | =水セメント比* |
|---|
X
| X線粉末法 (えっくすせんふんまつほう) |
粉末試料や多結晶試料のX線回折像を用いる物質構造研究法。各回折線の強度と散乱角から求められた面間隔*とを用いて試料を同定し、分析するために利用される。 |
|---|---|
| X線マイクロアナライザー (えっくすせん--) |
固体表面の微小部分の元素分析をする装置。XMAと略される。直径1μm以下に絞った電子線を試料表面にあて、そこから出てくる特性X線をX線分光器で測定する。その波長からは元素の種類、強度からは元素の含有量がわかる。電子線で試料面を走査して、元素の2次元分布を観測できる装置EPMA(Electron Probe Micro Analyzer)も使われている。 |
